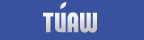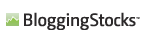ソニー VAIO Pの仕様流出、Atom Z520 + 2GB RAMで9万円前後?
ソニーがティーザー展開している「VAIO New Mobile」の仕様らしきものがリークされています。Eeepcnews改めnetbooknews.deが得た未確認情報によれば、VAIO New Mobile / VAIO Type P / PCG-1P1Lの基本仕様はAtom Z520プロセッサ、2GB RAM、HDDまたはSSDオプション、内蔵GPS、3G WWANオプション。価格は700ユーロ前後。そのまま現行レートで直せば約9万円。
SonyStyleでフライング掲載されていたときの仕様は「1.33GHz Intel processor」、Windows Vista、8インチ 1600 x 768 LEDバックライト液晶、60GB HDD または 128GB HDDオプション。「1.33GHz インテルプロセッサ」の正体は順当にいってSilverthorne Atom (Zシリーズ)、あるいは未発表の新CPUかも?と予測あるいは期待されていましたが、今回のリークが正しければやはりAtomだったようです。つまりプラットフォームとしてはWillcom D4やデルInspiron Mini 12とおなじMenlow (コードネーム) / Centrino Atom (旧ブランド名)。ただしRAMは2GB。
価格は700ユーロ前後とされているものの、いわゆる最小構成のスタート価格なのか標準構成なのかも分かっていません。バッテリーの容量も気になるところですが、国内では8万9800円スタートくらいでしょうか。